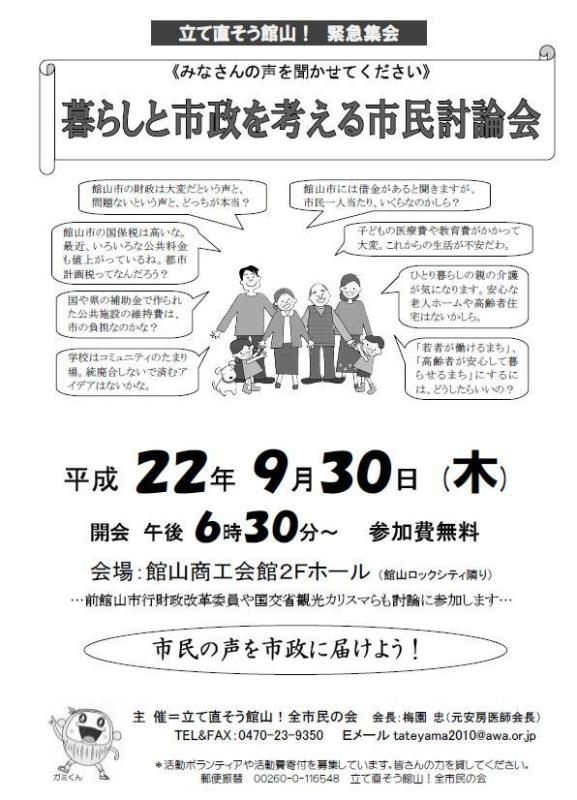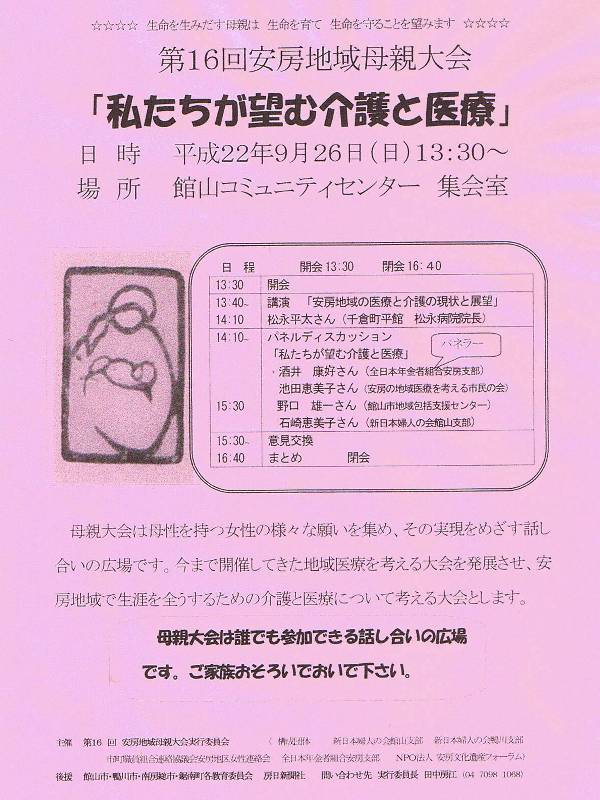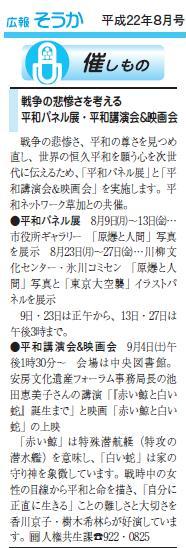10月16〜17日の「2010年ゆかりを訪ねる旅『館山の戦跡に学ぶ』」に参加し、赤山地下壕、128高地「戦闘指揮所」「作戦室」、「従軍慰安婦の碑」、米占領軍本隊本土初上陸地などを訪ねた。
NPO法人「安房文化遺産フオーラム」の愛沢伸雄代表は、軍部がアジア太平洋戦争時に①首都東京を守る重要な戦略拠点としてさまざまな軍事施設を建設②戦争末期には米軍上陸を予想、本土決戦陣地・特攻基地を造成③真珠湾と地形が類似する特性に着目し特攻作戦の訓練場として活用した事実を軍部作成の諸資料を駆使して詳細に解説した。
愛沢氏は、自らの人生そのものを費やした「房総半島南端の地が果たした歴史的役割の解明」「戦争遺跡を『未来遺跡』に」との熱い思いを汗だくで語ったが、1945年7月17日のポツダム会談と翌日の杉山元参謀総長の動きの指摘はリアルタイムで観ている錯覚をもつほど緊迫した雰囲気を醸し出した。
講演は、「戦争と平和」と「地域づくり」をキーワードに富士見地域に存在した「少年通信兵舎」へと話が及び、私は「地域から平和への発信を」との問題提起に強く胸をうたれたが、有事立法成立など「戦争は周到に用意される」との指摘に改めて緊張感の維持の大切さを痛感させられた。
(後援会ニュース原稿より)
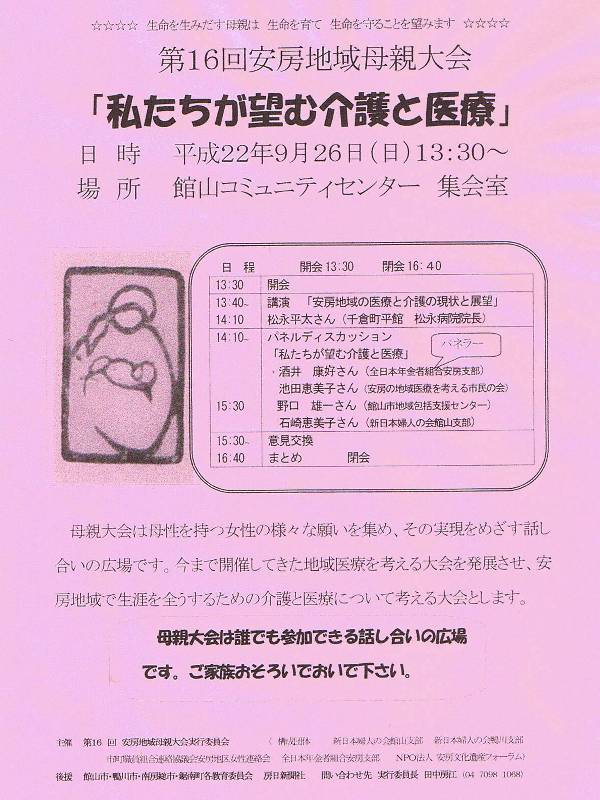
第16回安房地域母親大会
「私たちが望む今後と医療」
日時=平成22年9月26日(日)13:30〜
場所=館山市コミュニティセンター第一集会室
.
第一部:講演「安房地域の医療と介護の現状と展望」
・松永平太さん(松永医院院長)
第二部:パネルディスカッション
・酒井康好さん(全日本年金者組合安房支部)
・池田恵美子さん(安房の地域医療を考える市民の会)
・野口雄一さん(館山市地域包括支援センター)
・石崎恵美子さん(新日本婦人の会館山支部)
第三部=意見交換
まとめ=房州弁・憲法25条
■講演会*池田恵美子
・学校でも教えてもらえないことがわかり、とてもよかったです。子供と一緒にパールハーバーを見学してきてよかったです。
・貴重な資料をありがとうございます。よくわかりました。
・良い話をありがとうございました。めったに聞くことのない数々のお話、大いに語りついで下さい。
・私にとっては少し分からない話で残念です。戦争は絶対やってはいけないと思います。
・我が家は刀を供出しました。
・館山方面はあまり行ったことがないので知らないことばかりでしたので、よいお話でした。
・映画終わってすぐ話してほしかった。館山のことが分かり良かった。いい勉強になりました。
・知らなかった戦争の状況が解った。
・今回、4度目の座学ですが何度見ましてもこの歴史とともに友好のことにもふれて感動しています。
・館山のお話もとても興味深く感じました。
・知らないことばかりで大変勉強になりました。
・わかりやすく、聞きやすい講演でした。子どもや青少年にぜひ聞かせたい話ですね。
・知らないことばかりでいい勉強になりました。
・スライド&講演共に非常に興味深く聞きました。素晴らしかった。
・館山にも戦争遺跡があったのは知りませんでした。山口県にあるのは知っていました。”カイテン”の事です。全国にはいくつもあったのですね。
こわいですね。歴史的興味より嫌いだという、嫌悪感の方が大きいです。
・いろいろふるい歴史の事実を発掘されたことを聞き、有難かった。
・館山に関するお話、初めて知りました。?のきれいな所だとしか知りませんでした。
・以前、館山を通過し白浜に旅したことがありましたが、館山にはこんないろんな歴史があることを知り、大変勉強になりました。ありがとうございました。
・力強い活動に期待します。
・とてもくわしく、わかりやすい講演でした。なんにも知らずに生きてきてしまったなと気が付いた所です。伝えてゆかなくてはと思います。
・こんな講演はじめてで、とてもこの年で又、思い出せなかった面もありました。
・まとまりよく、情報量が多い講演でした。
■映画『赤い鯨と白い蛇』
・全く知らないことが映画を見たり、その後のお話でも、”そうだったんだ”と新たに認識できました。今日は大変勉強になり、思い切って来て良かったと思いました。ありがとうございました。
・女性(4人)の生き方が考えさせてくれました。声高ではなく戦争がもたらした悲劇をじっと味わえました。
・戦争を青春時代に経験した世代は、あのきびしかった時代を忘れられません。幾多の若い人々が死んでいった時代は一生心の片すみに消えることなく、涙と無念の思いでいっぱいです。戦争なき世の中をのぞみます。戦争で幸せになる人は一人もありません。
・73才になっての映画や色々な御苦労があっての映画作り、風景もとてもよく、感動しました。出演者もよかったです。又お願いします。
・私も田舎育ちなので共通点もあり興味深く、ありがとうございました。
・本当に静かなすてきな映画でした。
・とても良かった。昔の住んでいたことを思い出し、本当になつかしい。
・遠い昔の平和な時代、良き頃を思い出しました。田舎の風景、思い出しました。今、平和でありすぎる私達のため命をなくした方に感謝。
・館山の自然と共に本当に心にしみる映画でした。戦争のことなど実際に体験していないのですが、そういう時代に生きた人の思いも伝わってきました。
・この春、館山赤山壕など現地の方の案内で見ました。フォーラムの池田さんの座学でさまざまな歴史を学んでからの参加でより深く知ることができました。映画はぜぴ観たいと待っていました。とても感動しました。古民家に集まった4人の女たちの悩みと女性の戦後の生き方がつながっていることも。戦争中の館山のシーンはほとんど出てこなかったことは意外でしたが。自分に正直に生きなさい、生きたくても生きることを否定された人間の切実な遺言、今私たちも考えさせられました。
・とても映像が美しく、良かった。久しぶりに心の中からいやしの時間が持てました。
・久しぶりに戦争に関する映画を見ました。平和について考えてみたいと思います。
・大変、感動的な映画でした。タイトルの意味が良くわかった。
・とても良かった。感動しました。
・自分に正直に生きることの大切さを改めて思い知らされました。5人の女優さんの演技が素晴らしく、感動しました。
・戦争で悲しい事がいっぱいあったけれど、命は確実に未来に向けてつながっているのですね。私も白いへびを見た事があります。神様のお使いだと養母が教えてくれました。実の父は戦死、母は空襲で死んで、私は一人で生きてきました。やさしい養父母に育てていただきました。今、娘と?がいます。映画をありがとう。今日は参加できて良かったです。
・よくわからない。テーマが今一迫力にかけるかな。もう一度見ると新しい発見もあるかも知れない。
・両親の故郷が館山なので、とても身近なものとして拝見致しました。赤山地下壕は父と見学したこともあります。今まで知らなかったことが多々あり、勉強になりました。
・ゆったりと流れる古き良き時代風景で、心がなごみました。館山が戦争とかかわりが有る事も知りませんでした。良い映画をありがとうございます。
・人はそれぞれの人生があります。私も白い蛇を見たいと思います。見たくて見えるものではないと思います。戦争は絶対反対です。
・よかったです。改めて戦争が昔あったこと、そして若い命が失われていったことを忘れないでいたいと思いました。
・おもしろかった。自分に正直に。
・懐かしい映像と共に何かとても考えさせられました。自分を信じて自分に正直に…心に残る素敵な言葉です。
・女性の視点が興味深かった。
・しみじみと一人一人の心の動きがよめて、幸せな方向にむかい、よかったなと思いました。平和な中に戦争を考えさせられ、知らない事がたくさんあったのだと気が付きました。
・今の時代にそって考えさせられる、いい内容の映画でした。
・淡々としたいい映画でした。映画で伝えることがいっぱいあるので、図書館のホール活用を考えて欲しい。
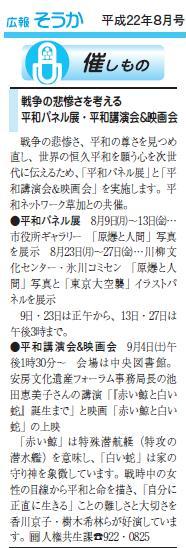
■平和講演会&映画会『赤い鯨と白い蛇』
…⇒詳細はコチラ。
戦争の悲惨さ、平和の尊さを見つめ直し、
世界の恒久平和を願う心を次世代に伝えるため、
「平和パネル展」と「平和講演会&映画会」を実施します。
平和ネットワーク草加との共催。
安房文化遺産フォーラム事務局長の池田恵美子さんの講演
「『赤い鯨と白い蛇』誕生まで」と映画「赤い鯨と白い蛇」の上映
「赤い鯨」は特殊潜航艇(特攻の潜水艦)を意味し、
「白い蛇」は家の守り神を象徴しています。
戦時中の女性の目線から平和と命を描き、
「自分に正直に生きる」ことの難しさと大切さを
香川京子・樹木希林らが好演しています。
【日時】2010年9月4日(土)午後1時30分〜
【会場】草加市中央図書館
【問合せ】草加市人権共生課048-922-0825
アフガニスタン・イラクと、アメリカのしかけた戦争に引きずられるように、日本の自衛隊派兵が拡大し、平和憲法の改正までもが堂々と公言されるようになりました。私は、日本がだんだん戦争を仕掛ける国へと変わってゆくようなこの流れに危機感を抱き、60年前の戦争について改めて考えてみようと思い、今回館山市で開かれたシンポジウムに参加しました。
振り返ってみれば、私は過去の戦争について学校で教わった記憶がほとんどありません。アメリカと戦争をして負けたこと、広島に原爆が落とされたことぐらいだったと思います。1985年私が二十歳のとき、そのころ横浜市に住んでいましたが、神奈川新聞に連載記事がのりました。私と同い年の在日韓国人二世の女性を追ったものでした。
なんで日本に生まれ育ち僕と同じ時代を過ごしてきたのに彼女は外国人登録証を持ち指紋押なつをしなければならないのか、なぜ彼女の住む川崎市には在日韓国・朝鮮人が多いのか、そんな疑問が過去の戦争の歴史を学ぶきっかけとなりました。その年はちょうど戦後40周年の節目のとしでした。当時は、戦争の傷跡を風化させてはならない、平和な社会を大切にしよう、そんな空気がマスコミにも社会にもあったと思います。(指紋押なつは1992年、永住者に限って廃止)
さて、シンポジウムに参加して初めて知ったことなのですが、館山市には47ヶ所もの戦争遺跡があり、さらに私の住む三芳村にもわが家から何㎞も離れていないところに、特攻機「桜花」のカタパルト発射台跡が残っているのです。
南房総は東京湾の入口にあたり、「本土決戦」が現実的な状況になってきた戦争末期に最も重要な地帯として位置づけられて、7万人に近い軍隊が配備され、さらには住民、学生、朝鮮人の強制労働も投入されて、燃料タンク基地、地下壕、航空機を隠す掩体壕(えんたいごう)、水中特攻兵器「海竜」基地、水上特攻艇「震洋」基地3ヶ所、魚雷発射基地4ヶ所、航空特攻機「桜花」発射基地などが建設され、8月15日の終戦までにすでにいつでも戦える態勢をほぼ終えていたということです。実はアメリカ軍は1946年3月1日に「コロネット作戦」と呼ばれる関東上陸作戦を予定していました。ですから、終戦がもし遅れたならば、房総半島南部は、1945年3月〜6月の3ヶ月間に日本兵約7万人、住民約1万人が亡くなった沖縄戦と同じ状況になったに違いありません。
房総半島で、本土決戦の準備が進められているのと同じころ、1944年10月に長野県松代(まつしろ)町(今は長野市)で延べ10キロあまりの巨大な地下壕の建設が始まりました。これは松代大本営と呼ばれています。大本営とは、戦時中に天皇が統師した軍の最高統師機関です。本土決戦に備えて、大本営と政府の主要機関を避難させる計画でした。そのうち天皇・皇后の居る場所は御座所と呼ばれて、一般には全く物のなかった時期に特別な建築材料が使われていました。終戦直前の1945年7月末には松代への移転の準備もできていましたが、実現しないまま終戦を迎えました。
前戦の兵士や住民を犠牲にして天皇や軍の指導者達はひたすら生き残ろうとした歴史的事実を示す場所として貴重な遺跡であるとの考えから、現在松代では保存運動と見学者へのガイド活動がすすめられています。
横浜市港北区日吉でも戦争遺跡の保存運動が行われていますが、マンション建設のため危機にさらされています。慶應義塾大学日吉キャンパスの下に延べ2.6㎞もの地下壕があります。地下壕とつながった地上の寄宿舎には連合艦隊の司令部が置かれ、地下の電信室では1944年9月から終戦までの海軍の作戦状況が手に取るようにわかっていたそうです。
慶應義塾では約3千人の学生が出陣して2千人以上が亡くなったといいます。
私たちは農業で暮らしています。農業は届けた作物を食べている人たちの平穏な日々を支える仕事だと思います。一方で年で暮らす人たちは、非常事態となれば日々の食事をとることさえ困難になることは、戦中戦後の歴史が教えてくれます(だからこそ現在の日本の食糧自給率40%は大変危ういことであって、年に暮らす人たちこそ、衰退する日本の農業の現実とこれからどうしたらいいかということを考えて欲しいと思うのです)。そんなわけで、農業の現場にいると戦争と平和について考えてしまいます。
過去の歴史事実と現在の政治の動向に無関心でいると、いつの間にか言いたいことも言えない世の中になってしまうのではないか、そんな心配をしています。皆さんも子どもたちの未来に責任を持つため、一緒に考えませんか。