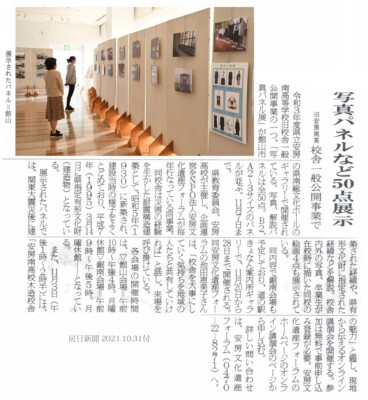連載コラム「館山まるごと博物館」012 (2022.1.18)
東京養育院安房分院と館山病院の転地療養 -渋沢栄一ゆかりの館山の人びと-
‥⇒リンクはこちら
(EICネット「エコナビ」一般財団法人環境イノベーション情報機構)
-400x191.png) ‥⇒シリーズ一覧【館山まるごと博物館】
‥⇒シリーズ一覧【館山まるごと博物館】
012「東京養育院安房分院と館山病院の転地療養 -渋沢栄一ゆかりの館山の人びと-
011「館山の空を飛んだ落下傘兵・秋山巌
010「青木繁『海の幸』誕生の漁村・布良」
009「明治期に渡米した房総アワビ漁師の古文書調査」
008「百年前の東京湾台風とパンデミック」
007「女学校の魅力的な木造校舎を未来に」 -旧安房南高校の文化財建築-
006「令和元年房総半島台風の災禍」
005「ピースツーリズム(2)-本土決戦と「平和の文化」-」
004「海とアートの学校まるごと美術館」
003「『南総里見八犬伝』と房総の戦国大名里見氏」
002「ピースツーリズム(1)-巨大な戦争遺跡・赤山地下壕-」
001「24年にわたるウガンダと安房の友情の絆」
安房地域母親大会
~女性の人権と戦争を考える ⇒ 詳細はこちら。
(房日新聞2022.1.16)⇒印刷用PDF@-290x400.png)
1月22日(土)1時半より館山市コミュニティセンターで、第27回安房地域母地親大会は住みよい地域づくりを目ざし、老若男女だれでも参加できる話し合いの広場です。不安の多いコロナ禍において、就労困難や貧困、DVや学力格差などはますます厳しくなっており、ジェンダー男女平等指数では日本が世界120位という状況にあります。
今大会はシンポジウム「女性の人権と戦争を考える」と題して、「かにた婦人の村(通称かにた村)」の名誉村長・天羽道子さんと、「希望のたね基金(通称キボタネ)」の代表理事・梁澄子(やんちんじゃ)さんをお迎えし、お話いただきます。
続きを読む »»
22日に館山コミュニティセンターで安房地域母親大会
(房日新聞2022.1.14付) ⇒詳細はコチラ。
-320x400.png)
第27回安房地域母親大会(同実行委員会主催)が22日午後1時半から、館山市コミュニティセンターを会場に開催される。今回は「女性の人権と戦争を考える」をテーマにシンポジウムが行われる。参加費無料で、資料代500円。定員75人で先着の予約制。
大会では、婦人保護長期入所施設「かにた婦人の村」・名誉村長の天羽道子さん、一般社団法人「希望のたね基金」代表理事の梁澄子さんを招き、第1部では2人のミニ講演、第2部では副実行委員長の池田恵美子さんをコーディネーターに対談を予定している。
続きを読む »»
「館山まるごと博物館」の挑戦 ~「平和の文化」のまちづくり
安房文化遺産フォーラム 池田恵美子さんに聞く
(ちば民報2021.12.5付)‥⇒ 印刷用PDF

千葉県館山市では、戦争遺跡(以下、戦跡)をはじめとする自然や歴史・文化遺産を「館山まるごと博物館」と見立てて、市民が主役のエコミュージアムまちづくりを進めている団体があります。NPO法人「安房文化遺産フォーラム(以下、フォーラム)」です。エコミュージアムとは、市民が主体的に研究・展示・保全などの活動を通じて活性化を図るまちづくりの手法です。
フォーラムは、高校世界史教諭だった愛沢伸雄さんが戦跡を活用した平和学習を契機として、市民による文化財保存運動を経て設立されました。長く事務局長を務めた池田恵美子さんは、今年度より共同代表になりました。
今回、池田さんが千葉県立館山総合高校の1年生を対象に「観光の学び」の講義をするというので、同席して聴講し、お話を伺いました。
続きを読む »»
明治のアワビ漁師に思いはせ
南房総千倉の旧家など散策
渡米した足跡探る
-233x400.jpg)
旧家を見学しながら、およそ二キロの散策ルートを楽しんだ。(山田雄一郎)
ウオーキングを開催したのは、地元のNPO法人安房文化遺産フォーラムなど。歴史を知り、先人たちの姿から地域活性化のヒントを探ろうと、南房総市の市民提案型チャレンジ事業として行われた。同フォーラム関係者がガイドを務め、太平洋沿いの国道近くに立ち並ぶ旧家を見て回った。
ある旧家では、モントレー湾から持ち帰ったアワビの大きな貝殻が軒先で示され、ふだん目にする地元のアワビとは違った大きさに参加者は驚きの表情を見せ、手に取って確かめた。散策ルート上には、兄がアワビ漁師として渡米した、日本人初のハリウッド俳優早川雪洲の旧家も。近くのミニ博物館では、日米親善の国旗が描かれた大漁祝い着「万祝(まいわい)」やモントレー湾での様子などを撮影した写真に目を留めた。
東京都内の大学に通う佐野一成さん(21)は館山市出身。NPOの運営などに関する卒業論文をまとめるため、ウオーキングに参加した。アワビ漁に携わった旧家が密集して残る様子に触れ「昔の地域コミュニティーの在り方が分かって面白かった」と振り返った。
同フォーラムによると、一八九七(明治三十)年、根本村(現・南房総市白浜地区の一部)出身の小谷源之助(一八六七〜一九三〇年)・仲治郎(一八七二〜一九四三年)兄弟らがモントレー湾の豊富なアワビ漁に注目し、渡米。アワビステーキや缶詰などで成功を収めた。漁師たちは日本人コミュニティーをつくり、ゲストハウスには尾崎行雄、竹久夢二ら政治家・芸術家が訪れ、日米親善に寄与した。仲治郎は帰国し、現在の南房総市千倉地区で潜水技術者を養成し、米国に住む源之助のもとへ送り込んだ。
館山総合高校1年生97人が観光の学び
戦跡や文化財を見学
(房日新聞 2021.11.19付)‥⇒ 印刷用PDF
-1-244x400.jpg)
14日にウォークイベント_参加者募集
房総アワビ移民研究所
(房日新聞2021.11.11付)‥⇒印刷用PDF
_page-0001-400x400.jpg)
房総アワビ移民研究所によるイベント「渡米したアワビ両紙たちのふるさとを訪ねよう」が、11月14日午前10時半~正午、南房総市千倉町大川の七浦診療所をスタートに開かれる。参加者を募集している。参加者無料。
同研究所は、明治期に安房地域から渡米したアワビ移民の歴史を掘り起こし、後世に伝えようと、地域に残されている古文書を読み解き、調査研究を深めている市民団体。歴史文化や功績を明らかにすることで、地域振興や国際交流の活性化につなげようと活動しており、同市の令和3年度市民提案型まちづくりチャレンジ事業のチャレンジコースに採択されている。
今回は、NPO法人安房文化遺産フォーラムと明治時代のアワビ漁師らのふるさとを訪ねるウオーキングイベントを企画。まちかどミニ博物館(同市千倉町千田)の見学もある。
小雨決行、荒天の場合は中止。
また、同研究所は14日まで、同市の三芳農村環境改善センターで行なわれている南房総市文化祭で資料などを出展。古文書の調査内容などをパネルいまとめ、展示している。
イベントの申し込み、問い合わせは、同研究所の鈴木さん(090-5812-3663)へ
⇒ ウォーキングの詳細はコチラから。
安房南高校旧第一校舎の価値紹介
千葉県教委らオンライン講演会
(日刊建設工業新聞社_2011.11.5付)‥⇒印刷用PDF
【関連ページ】オンライン講演会&写真パネル展
-400x400.jpg)
旧安房南高 校舎一般公開事業で
写真パネルなど50点展示
(房日新聞2021.10.31付)‥⇒ 印刷用PDF
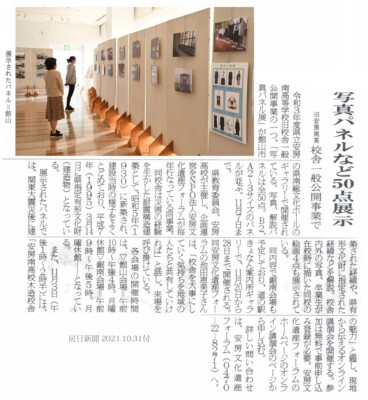


-400x191.png)
@-290x400.png)
-320x400.png)
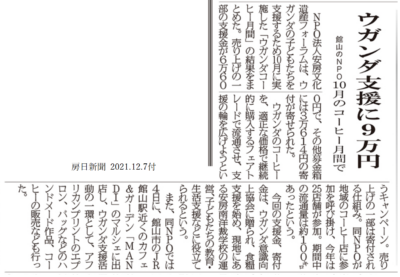

-233x400.jpg)
-1-244x400.jpg)
_page-0001-400x400.jpg)
-400x400.jpg)