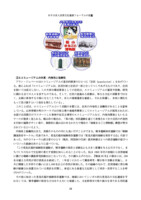【論文】長谷川曾乃江
戦争遺跡を活かした館山のエコミュージアム
長谷川曾乃江(中央大学兼任講師)
⇒ 印刷用PDF ⇒ 『ヘリテージまちづくりのあゆみ』収録
1.はじめに
房総半島南部は江戸時代から政治的・経済的に東京(江戸)との密接な関係を持っており、明治以降も帝都・東京から近距離にあるため、軍事施設が多かった。とりわけ東京湾の入口に位置する安房地域は、対岸の三浦半島とともに砲台が設置されるなど、「東京湾要塞」の一部を成していた。館山市では、洲崎第1砲台(1932年完成)、洲崎第2砲台(1927年完成)、すぐ北側の南房総市(旧富浦町)に大房岬砲台(1932年完成)が造られ、館山海軍航空隊(1930年)、館山海軍砲術学校(1941年)、洲ノ埼海軍航空隊(1943年)及びそれらの関連施設が数多く置かれた。
館山市では1990年頃から、地元の歴史教育者や市民有志がこれらの戦争遺跡の調査研究活動を積み重ねてきたが、そうした流れを受けて2002年には、市行政が戦争遺跡を平和学習拠点としてまちづくりに活用する構想を具体化しはじめた。この時の調査報告書『平和・学習拠点形成によるまちづくりの推進に関する調査研究―館山市における戦争遺跡保存活用方策に関する調査研究―』には、戦争遺跡を他の歴史・文化遺産(古代以来の安房文化や戦国時代の里見氏関連史跡等)とともに「地域まるごとオープンエアミュージアム・館山歴史公園都市」として保存・活用していく具体的なプランが提示されている。
この「地域まるごと」という概念は、「エコミュージアム」という理念に発想を得ている。「エコミュージアム」は、フランスで生まれた「エコミュゼ(Ecomusée)」の英語訳で「環境博物館または生態学博物館」(鶴田総一郎)・「生活・環境博物館」(新井重三)等の訳語が与えられてきたが、日本では1990年代以降、各地でまちづくり計画に採用されてきた。その意味は伝統的な箱モノ管理に限定された「ミュージアム」事業とは異なり、地域に存在する自然遺産・文化遺産・産業遺産などを行政・住民・専門家の連携によって(箱モノも含めて)ネットワーク化し、それらを保存・活用すると同時に地域の活性化につなげていこうとする活動とその成果をさす。
館山における戦争遺跡とエコミュージアムの結びつきには、次のような特徴がある。
(i) 2000年代の比較的早い段階で市行政がエコミュージアム構想を明確に打ち出した。
(ii) その受け皿として、民間団体や市民による長年の保存運動を通じてエコミュージアム的志向が自然に生まれていた。
(iii) 戦争遺跡に対するイデオロギー的過敏さが他の地域より少なく、市の政策に対して組織的な反対運動がなかった。
本稿の目的は、館山市における戦争遺跡の保存・活用が、どのような経緯や背景でエコミュージアム化されてきたのかを詳しく考察することである。
2.館山市の戦争遺跡への取り組み
① 文化財保護法による戦争遺跡再評価と館山市の戦跡調査
1995年2月に文化財保護法が改正されるまで、近代戦争遺跡は文化財指定の対象ではなかった。また、遺跡保護の基準となる「周知の遺跡」の時代範囲は都道府県によって異なり、千葉県ではおおむね中世までとされたため、館山の戦争遺跡は法的保護の外に置かれていた。
しかし、1995年に同法の史跡指定基準が改正され、第二次世界大戦終結時までの戦争遺跡も文化財指定の対象となると、1996年度から文化庁による「近代遺跡総合調査」が始まり、1998年度には「政治・軍事」分野を対象とする所在調査(戦争遺跡の所在を都道府県に問い合わせ確認する調査)が実施された。こうして戦争遺跡が近代の歴史を理解する上で欠くことのできない重要な遺跡と評価されるようになると、館山市も独自の指針による文化財指定の条件整備を進め、1980年代に市立博物館が行った戦争体験者からの聞き取り調査などを基礎に、1997年から2ヶ年かけて戦争遺跡の所在確認調査を行った。
その結果は1999年7月の館山市文化財審議会で審議され、建造物として指定に相当する戦跡はないこと、その他の遺跡については史跡指定は時期尚早だが、地域の歴史遺産として評価できるよう継続調査が必要との意見が具申された。
一方、「戦後50年」の節目となった1995年前後には、地元の教員組織や市民が中心となって「戦後50年・平和を考える集い」実行委員会を結成し、戦争遺跡のフィールドワーク、講座、企画展などを自発的に展開するようになった。また、館山市広報のグラフ誌『ルックたてやま』でも特集「館山にとっての戦後50年」を組み、市内の戦争遺跡を紹介した。こうして、市民と行政がそれぞれの活動を通じて、館山の戦争遺跡を見直していく契機となった。
これらの活発な動きを背景に館山市は2002年、(財)地方自治研究機構と共同調査研究事業を行った。その成果が上にあげた調査報告書『平和・学習拠点形成によるまちづくりの推進に関する調査研究―館山市における戦争遺跡保存活用方策に関する調査研究―』である。ここでは、将来、文化財としての保存及び活用が見込まれる戦争遺跡47ヵ所がリストアップされた。文化庁が示した近代遺跡評価方法に従うと、Aランク(近代史を理解するうえで欠くことができない遺跡)18ヵ所、Bランク(特に重要な遺跡)13ヵ所、Cランク(Aランク・Bランクの遺跡群に属する遺跡のうち残存状況の悪いもの、あるいは消滅等により確認できないもの)16ヵ所という評価が下された。全国的にも類例が少ないAランクの遺跡が館山に数多く現存していることがわかったのである。
② Aランク遺跡とその保存・活用
Aランク遺跡として重要性が認められたものは、館山海軍航空隊(通称「館空(たてくう)」、以下「館空」と略)や館山海軍砲術学校(通称「館砲(たてほう)」、以下「館砲」と略)に属する遺跡群、及び西岬地区に設置された東京湾要塞の砲台等である。
「館空」は1930年、横須賀・佐世保・霞ヶ浦・大村に続き、全国で5番目の航空隊として開設された。現在は海上自衛隊館山航空基地の敷地となっている。日中戦争時、この航空隊で訓練され,その後木更津航空隊所属となった九六式中型陸上攻撃機(通称「中攻」)部隊が「渡洋爆撃」と呼ばれる中国都市への無差別攻撃を実施し、「館空」は大陸に向けての航空戦略の重要拠点となっていった。また、ここの滑走路は房総特有の西風を強く受けるように配置され、航空母艦の短い甲板からの離着陸訓練(タッチ・アンド・ゴー)に最適であった。ハワイ真珠湾攻撃に投入されたパイロットたちは、この航空隊で高度な操縦訓練を受けていたという。本土決戦に備えては、帝都に近い房総半島全域が最重要地域となったため、「館空」とその付属施設である赤山地下壕の周辺で、民間人や朝鮮人を動員して巨大な燃料タンク基地や掩体壕の建設が突貫工事で進められた。
館山海軍航空隊赤山地下壕跡(以下、「赤山地下壕跡」と略)は「館空」本庁舎(現在の海上自衛隊館山基地本庁舎)のすぐ南側にある標高60メートルの小高い山で、現在も凝灰岩質砂岩などから成る岩山の中に、総延長2キロメートル近くの地下壕と燃料タンクが残っている。この地下壕に関わる資料は不明なため、建設時期や建設方法、どのような施設として利用されていたのかは明らかではない。しかし、「館空」の戦闘指揮所や野戦病院として利用されていたという証言があり、また壕内部の形状から、司令部・奉安殿・戦闘指揮所・兵舎・病院・発電所・航空機部品格納庫・兵器貯蔵庫・燃料貯蔵庫等の施設を合わせ持つ、全国でも珍しい航空要塞的な壕だったのではないかとも考えられている。
赤山地下壕跡の裏手にあたる宮城地区には戦闘機用掩体壕があったが、現在は鉄筋コンクリート製掩体壕が1基残っているだけである。これは河岸段丘の地形を利用したもので、屋根部分に土が盛られ草を植えてカモフラージュしてあるため、上空からは見えづらい。
「館砲」は、海軍が行う陸上戦闘の将兵養成機関として1941年に開校された。入校後の訓練は陸戦・対空・化学兵器の三科に分かれ、化学兵器科では,海軍唯一の細菌戦・毒ガス戦の訓練も行われていた。
洲崎(すのさき)第1砲台は、1932年に竣工した45口径30センチカノン砲2門入り砲塔1基(巡洋艦「生駒」の主砲を転用)が置かれたもの、第2砲台は1927年に竣工した7年式30センチ榴弾砲4門が配備されたものである。また、これらの砲台を主とした砲弾や炸薬を貯蔵管理していた重要施設が、洲崎弾薬支庫であった。
これらAランク遺跡の中で館山市はまず、赤山地下壕跡の保存・整備・公開に取りかかった。同地下壕は全国的に見ても大規模な防空壕跡であり、館山市を代表する戦争遺跡であると評価されたからである。この場所は戦後払い下げられた市有地(公園用地)だが、長い間放置され、壕内にはキノコの研究・栽培のために30年以上居住している人がいた。市民団体による見学・学習もその人の承認を得て行われていたが、当人の死亡に伴い地権の問題はなくなった。地下壕跡の活用については市議会でも取り上げられ、行政による模索が始まった。市当局や市議会総務委員会が視察を行い、安全対策などを検討し始めた。
その結果、前述した2002年の(財)地方自治研究機構との共同調査研究事業が実現し、翌年には安全性確認のため本格的な地質調査が実施された。その後、従前の見学活動をふまえて安全対策を講じた一般公開ルート(約250メートル)を設定し、供用に向けて危険箇所の補強工事と照明・放送設備等の整備工事を行った。2004年には市による一般公開が開始され、入壕者の安全と円滑な管理運営を図るため、都市計画課が月1回の定期点検と年1回の専門家による詳細な点検などを行うようにした。また、文化財としての管理のため、教育委員会生涯学習課が地下壕跡の北側にある社会教育施設(通称「豊津ホール」)を提供し、受付業務・駐車場・トイレ利用に役立てるようになった。見学者は入壕の際、同ホールで注意事項を確認し入壕届を提出してから、安全のためにヘルメットの着用が義務づけられている。
③ 赤山地下壕跡を中心とする戦跡ネットワーク化計画
2014 年、赤山地下壕跡は公開 10 年を迎えた。入壕者は年間約2万人近くに達し、その半数は県内外から館山市を訪れる人びとで、市の観光にも大きな成果を上げている。市は財政難のなかで保存・管理を続けるために入壕を有料化し(現在大人 200 円)、その結果、大型バス用の駐車場も整備された。
修学旅行その他団体見学のガイド活動は、NPO法人安房文化遺産フォーラム(以下「NPOフォーラム」と略)が行っている。NPOフォーラムが推奨し、これまで実施してきた見学コースは、約1時間の座学を通して戦時下の館山について学習した後、メインの赤山地下壕跡とともに、戦闘機用掩体壕、終戦直後の米占領軍上陸地点(「館空」水上滑空台跡)など重要な周辺遺跡を現地見学するという内容である。
洲ノ埼海軍航空隊(通称「洲ノ空(すのくう)、以下「洲ノ空」と略)は 1943 年に開設された全国で唯一の兵器整備練習航空隊で、操縦以外の航空機に関わる専門技術(開発・整備・管理)を学ぶ養成機関である。その射撃場跡では、戦闘機用機銃のプロペラ同調発射装置の実弾発射テストが行われ、今も弾丸が刺さったままの痕跡がある。また、「128(いちにはち)高地」は本土決戦の作戦命令によって建設されたと考えられる抵抗拠点のひとつで、現在は福祉施設敷地内の小高い山にある地下壕跡である。その内部には「戦闘指揮所」「作戦室」の文字などが浮き彫りにされたコンクリート製の額や、天井に彫られた龍の大きなレリーフをはっきり観察することができる。
館山市の計画では、赤山地下壕跡を平和学習拠点の「核」と位置づけ、ここを中心として周辺の遺跡をサテライト化するような、「館空」関連遺跡のネットワークを同地域に形成し、ハード面(遺跡保存・活用の物理的な整備)・ソフト面(遺跡維持・管理・見学・学習を円滑化する仕組み)の両方を充実させていくことになっている。
しかし、ハード面については赤山地下壕跡以外の遺跡はいわば「保存・公開物件予備軍」の段階であり、実際に見学が行われているとはいえ、安全対策や保存・維持費用、地権者や地元住民の了解というハードルがあるため、いまだに制度的な実現は進んでいない。一方、ソフト面でも課題が残っており、例えば赤山地下壕跡の活用については縦割り行政(教育委員会生涯学習課・商工観光課・都市計画課等の横断的管轄)の弊害が否めない。市行政がNPOフォーラムなどとどう連携すれば、地域活性化の取り組みやガイド活動を円滑に支援できるかが問題である。
④ 戦争遺跡を活かすエコミュージアム構想
館山市による戦争遺跡保存・活用の進捗状況は赤山地下壕で止まっているのが現状だが、ここで館山市のエコミュージアム構想を概観してみたい。上の調査報告書では「歴史資源等を活かした平和・学習拠点の可能性と在り方」として、戦争遺跡を地域の中でどのように活かしていくべきかが述べられている。そこに見られるエコミュージアム的な視点を要約すると、次のようになる。
- 市民が戦争遺跡を歴史遺産として自分たちのために永続的に保存継承・活用すること(学校教育・生涯学習)と、来訪者や外部者に対して戦争遺跡を紹介し独自の市民文化・地域の個性をアピールすること(観光・修学旅行)は表裏一体である。
- 館山の戦争遺跡をより広域に捉える。すなわち、江戸あるいは帝都・東京と東京湾防衛を軸とする地政学上の立地条件から、旧海軍の中枢・横須賀、東京とその周辺、隣接地域の南房総市(旧富浦町)大房岬まで射程に入れた上で、館山の戦争遺跡を位置づけることが重要である。
- このような、戦争遺跡を組み入れた都市づくりの目標像を「地域まるごとオープンエアミュージアム(フィールド博物館)・館山歴史公園都市」と設定し、まちづくりの方向を象徴的に示すものと考える。
- 時間的には、古代の安房から戦国時代の里見氏、江戸期の紀伊半島との水産・交易、幕末江戸防衛の先端地域、明治以降の東京湾要塞、太平洋戦争の本土防衛の先端地域といった時間軸に、近代戦争遺跡をあらたに組み入れた歴史を考える。
- 空間的には、館山海軍航空隊・洲ノ埼海軍航空隊群遺跡、東京湾要塞群遺跡、館山海軍砲術学校群遺跡という3つの大きな戦争遺跡群として系統化し(整備時期や関連性から、遺跡の一部は空間的に重層化している)、各拠点にそれぞれ核となる施設を設けるとともに、周辺地域の観光施設とのネットワーク化も行う。
これらの視点は、5年ごとに見直される「館山市基本計画」においても明確に示されてきており、 2011 年度の『館山市基本計画』では「歴史遺産である戦争遺跡を活用した特色ある地域文化の発信と観 光振興」を課題とし、「戦争遺跡を、館山の歴史を知るための歴史遺産として位置付け、市民や来訪者の歴史学習や平和学習に活かすため、広く市民の理解と協力を得ながら、その保存と活用に努めます。また、環境の整備がすすむ『赤山地下壕跡』に加え、周辺の戦争遺跡を保存するための環境を整備し、見学ルートを整備するなど平和学習の場を広げます。」という具体的な事業概要が掲げられている。そして、戦争遺跡以外に館山市を牽引していく歴史遺産として、里見氏などの歴史文化をまちづくり・ 観光・文化交流・伝統継承の主要な柱とすることが要所要所で宣言されている。
3.草の根戦跡保存運動に見るエコミュージアム的志向性
① 戦跡保存運動と里見氏稲村城保存運動の結びつき
全国的に見ると戦争遺跡への対応に保守的・消極的な自治体が多い中、館山市ではまちづくりや観光資源など地域活性化の手段として行政が戦争遺跡に着目し、エコミュージアム的な基本構想に組み込んでいることは高く評価できる。
だが、館山における戦跡保存・活用の進歩的な風向きがつくり出された背景には、草の根の地道な活動があった。戦争遺跡の保存やエコミュージアムといった観念は時代の要請から生まれた流れであるが、地域に根ざす課題やニーズを最初に感じ取り意識化していくのは、多くの場合、市民らの日常的な感性だからである。
戦争遺跡に関していえば、文化財保護法改正によって近代戦争遺跡も法的保護の対象となった 1995年頃から、全国的に戦争遺跡保存の声が高まってきていた。1997 年、日本各地の保存運動を取り結ぶ「戦争遺跡保存全国ネットワーク」が結成され、以前から戦争遺跡に関わってきた歴史教員などを中心に、関心を持った一般市民の間でも運動の組織化や情報交換が進みはじめる。
館山市では、地元高校の教諭であった愛沢伸雄が 1989 年から戦争遺跡の調査研究を開始し、歴史教育者の研究会で、戦争遺跡に関わる地元教材による授業実践を報告していた。また、「館砲」の戦争遺跡について山口栄彦が『消えた砲台―少年と館山砲術学校』(東銀座出版、1991 年)を発表したことを受け、愛沢と山口は地元高校の郷土研究部を指導して、1993 年の「学徒出陣 50 周年」に関わる展示会を開催した。これをきっかけに、1995 年には「戦後 50 年」をめぐる催し(フィールドワーク・講演会・証言の会)に市民の主体的な参加が見られるようになり、1996 年頃からは市民らの手による継続的な戦跡保存の取り組みが行われるようになった。
館山地区公民館講座の講師も努めていた愛沢はその後、戦跡フィールドワークやウォーキングを通 して戦跡保存に目覚めた有志たちとともに、2003 年、館山地区公民館の登録団体「戦跡調査保存サークル」を結成した。実はこのサークル参加者が中心となって、館山市当局や市議会に対して赤山地下壕跡などの保存活用を訴えると同時に、隣りまちである富浦町(現南房総市)の千葉県立大房岬自然公園内にある大房岬砲台の保存と史跡化についても、町当局と教育委員会に保存と史跡化を働きかけていた。その結果、2001 年7月、東京湾要塞大房岬砲台跡など 12 件が富浦町指定文化財となり、県内での戦争遺跡指定第 1 号となった。
他方で愛沢は 1996 年当時から、里見氏稲村城跡保存運動にも関わり始めた。稲村城は房総里見氏が15 世紀後半に安房国を平定した時期の本城であり、安房地域にとってはシンボル的な文化遺産である。この運動は、市道建設によって破壊される寸前であった稲村城跡を守るためのもので、愛沢は急遽「里 見氏稲村城跡を保存する会」を結成し、城跡内を通る市道計画ルートの変更を訴えるとともに広く周囲に呼びかけた。その結果、全国から約 1 万筆の署名が集まり、また市議会に対する7回の請願書も功を奏して、2年がかりで城跡の破壊を止めることができた。さらに運動成功後は稲村城跡1ヵ所だけでなく、他の城跡も含む里見氏城郭群として国指定史跡を目指し。保存・活用の取り組みを続けていった。
2004 年、「戦跡調査保存サークル」と「里見氏稲村城跡を保存する会」がともに母体となって、現在のNPO法人安房文化遺産フォーラム(旧名称:南房総文化財・戦跡保存活用フォーラム)が設立された。
NPOフォーラムのねらいは、単に戦跡保存と文化財保存の運動を合流させることではなかった。 NPOフォーラムは発足当初から赤山地下壕跡など館山地域の戦跡ガイド活動を行うだけでなく、地 域のフィールド全体を「地域まるごと博物館」と見立て、安房の自然遺産・文化遺産・歴史遺産を再発見するとともに、市民が主役となった学習・研究・展示や保存活動を通じて地域づくりに活かしていくという、まさにエコミュージアム的理念を標榜してきた。実際、NPOフォーラムでは里見氏や稲村城跡をめぐる歴史文化を追求して数々の講座やイベント、周知活動に努力するだけでなく、「戦後 60年」のタイミングでは日米・日韓平和交流を行ったり、近年では富崎地区の住民とともに青木繁「海の幸」誕生の家と記念碑を保存する会を結成し、地域づくりの視点から文化財の保存運動を展開している。館山ではこうした草の根の運動が根気強く継続されてきたからこそ、地域資源を観光に活かすことに着目した行政側の構想とうまく連動したのであろう。
② エコミュージアムの本質:内発性と協働性
アラン・ジュベールはエコミュージアムの基本的要素のひとつに「住民(population)」をあげている。彼によれば「エコミュージアムは、住民行政と住民が一体となってつくりあげるものであり、住民を除いては成立しない。この大切な構成要素としての住民は、エコミュージアムの運営や活動、研究に関わる全ての人々を表すものである。そして、住民の意義ある活動は、単なる文化の消費者ではなく、企画に参加する立場になることであり、自らの地域遺産を確認し、それを保護し、未来に責任をもって受け渡すという役目を果たしている」。
このことばは、エコミュージアムという実践の本質には、住民の内発性と協働性があることを意味 している。山形県朝日町のケースでは行政主導の地域再興策としてエコミュージアムが採用されたが、全国では民間だけでスタートした事例や住民主導型のエコミュージアムなど、内発的開発ともいえるケースが数多く見られる。館山市の場合は、「草の根」市民運動を通じて表現されてきた住民の内発性を行政の施策がすくい取り、制度的に重ね合わせるかたちで現在の「地域まるごと博物館」構想が明示されているといえよう。
内発性と協働性はまた、実践そのものの中にも見いだすことができる。戦争遺跡保存運動では「戦跡調査保存サークル」代表であり、里見氏稲村城跡保存運動では「里見氏稲村城跡を保存する会」代表であった、NPOフォーラム設立者のひとり(現在、同団体の代表)愛沢伸雄は2つの保存運動が結びついていった経緯を次のように述べている。
「この里見氏稲村城跡保存運動が、戦争遺跡の保存と史跡化にも大きく影響を与えるだけでなく、まちづくりのなかで文化財の果たす役割を知らしめることになった。私は 1990 年代の初頭から安房地域
に置ける戦跡の調査研究活動をおこなっていた。その積み上げのなか、『戦後 50 年』の節目には、200名を越える市民が実行委員会を結成して、1年近くにわたって調査研究・聞き取り活動を実施し、8月に開催した手作りの集いには 1,000 名以上の市民が参加した。その経緯のなかで、安房地域に残る戦跡が破壊され放置されている現状を打開し、身近にある貴重な文化財として保存・活用することを呼びかけていった。
その後に始まった里見氏稲村城跡保存運動では、地域においてシンボル的な里見氏の文化遺産を守れなくては、戦争遺跡の保存などはありえないと痛感した。文化財保存の取り組みを実りある市民運動にしていくためにも、たとえ時代が違って、その歴史・文化も違う文化財であっても、文化財を守っていくという一点で力を合わせることを強く訴えていった。私は2つの保存運動を並行して進めていくことで、互いに相乗効果ができるような文化活動を企画していった。」
ここでは、中世城郭の稲村城跡と戦争遺跡という異なる文化遺産を同時に守ることで、あるがままの歴史の重層性に気づき、その時間・空間のなかでこそ自分たちが生きている実感を受けとめるとともに、それを表現し実践していくという、きわめて内発的な過程が見てとれる。また、それは運動のなかで他者に呼びかけ、力を合わせていく協働性へと自然に結びついていく。
そもそもエコミュージアムの思想的背景は、1970 年代のフランスにあった。当時のフランス社会では高度経済成長の弊害として、急激な都市化と農村の過疎化、環境破壊と人間性の喪失感、精神的荒廃などの現象が見られた。それに対して中央集権の否定と地方分権への期待、環境保護や地域主義がうたわれ、国土整備政策の実施とともに住民の主体的な活動も盛んになっていった。そこから、それぞれの地域に密着して生き、地域の姿を理解するという価値観が登場した。同様の発想は 1980 年代末から 1990 年代以降の日本でも受け入れられ、定着していった。バブル経済崩壊と高度情報化社会、都 市と農山村のバランス喪失のなかでの人心の精神的疲弊が叫ばれ、地域の自律性と住民活力の創出や、環境づくりを通した人間性の回復が求められていたからである。コミュニティ、アイデンティティ、 ネットワークという横文字が至るところで使われ、地域共生と自分探し、横のつながりが一体のものであることが強調された。さまざまな自治体で、地域づくり・まちづくりと住民参加を生涯学習と組み合わせる試みが行われるようになった。
今日、地域共生における内発性と協働性の重要性は、いっそう増している。グローバリゼーション が進行するとともに人々の意識はより小さな共同体へと回帰し、そこで自己と地域の個別性・特殊性を、目の前にある素材でいかに再構築していくかが課題となっているからである。エコミュージアムが遺産という「モノ」への働きかけであると同時に、実は自分にも他者にも再びつながろうとする実践、すなわち「ヒト」との結びつきであることが、今後も重要な視点となっていくだろう。
4.結びにかえて
最後に、エコミュージアムが地域共生における内発性・協働性を基礎としたものであることを念頭においたうえで、戦争遺跡という歴史遺産を組み入れていく意義や課題などを考えてみたい。
元来、戦争遺跡には軍事施設の遺構や構造物(トーチカや地下壕、要塞、工場、飛行場、軍港、掩体壕など)が多く、野外博物館的な性質を持つため、エコミュージアムの概念には非常によくなじむ。しかも、戦争遺跡を他の自然・歴史・文化遺産等と切り離さずに理解するエコミュージアムの発想は、戦争遺跡のより深い学習にもつながる。
第一に、地域の個性を戦争以外の側面からも観察することで、戦争遺跡の背景を多角的・総合的に理解することができる。第二に、重層化された時間を通して学び理解することで、戦争と平和、破壊と創造(文化)を対比させ、戦争の意味をより深く考えることができる。そして何よりも、一般化された戦争ではなく、その地域に生きる人間にとって戦争とは何だったのか、平和とは何なのかを考えるきっかけとなる。
館山市で戦争遺跡の保存・活用やエコミュージアムへの組み入れが進んだ理由のひとつには、「負の遺産であっても継承する」という市行政の明確な姿勢があった。その背景には戦争遺跡が観光資源として見込まれるという判断も含まれていたが、戦争に対してイデオロギー的に過敏ではない地域性も幸いした。地域と戦争の関わりに敏感な地域では、地域のアイデンティティや平和行政のありかたをめぐって根源的な対立が表面化する場合が多いからである。
いずれにしても、戦争という地域体験はその住民にとって非常に重要な意味を持つことは明らかであるから、戦争遺跡をどのようなかたちでエコミュージアムに組み入れていくにせよ、そこには地域と戦争のつながりを深く意識し、あらためて現実の平和文化をいかに構築していくかという重要な課題がある。さらに今後、少子高齢化・過疎化が進行するなかでどのようにして住民活力を開発していくかが問われるであろう。限りある公的財源を無駄なく利用するために、これまでのハード(箱モノなど)重視の政策ではなく、ソフト(人的ネットワークや人材養成)重視への方針転換が必要であり、また誰にとっての継承価値かという視点や、合意形成における民主的プロセスの再確認も必要であると思われる。
【主要参考文献・資料】
*戦争遺跡全般と館山の戦争遺跡について
・戦争遺跡保存全国ネットワーク編『戦争遺跡から学ぶ』岩波書店(岩波ジュニア新書)、2003 年
・戦争遺跡保存全国ネットワーク編『保存版ガイド日本の戦争遺跡』平凡社(平凡社新書)、2004 年
・千葉県歴史教育者協議会編『千葉県の戦争遺跡をあるく』国書刊行会、2004 年
・NPO法人安房文化遺産フォーラム『あわがいど①戦争遺跡南房総に戦争の傷跡をみる』2004 年
・(財)地方自治研究機構/館山市『平和・学習拠点形成によるまちづくりの推進に関する調査研究―館山市における戦争遺跡保存活用方策に関する調査研究―』2003 年
・杉江敬(館山市教育委員会生涯学習課)「平和学習施設としての近代戦争遺跡の保存と活用」
(『地域政策研究』第 30 号、2005 年3月)
・館山市市長公室企画課編『館山市基本計画(2011)』千葉県館山市、2011 年3月
*エコミュージアムについて
・『ECOMUSEUM』丹青研究所、1993 年
・日本エコミュージアム研究会編『エコミュージアム・理念と活動―世界と日本の最新事例集―』牧野出版、1997 年
・大原一興『エコミュージアムへの旅』鹿島出版会、1999 年
*里見氏稲村城跡保存運動とNPOフォーラムの諸活動について
・愛沢伸雄「市民による『稲村城跡保存運動』は実った」(『歴史学研究』第 712 号、1998 年7月)
・愛沢伸雄「『安房・地域まるごとミュージアム』構想とNPO活動」(『足もとの世界から世界を見る―授業づくりから地域づくりへ』NPO法人南房総文化財・戦跡保存活用フォーラム、2006 年)
・愛沢伸雄・池田恵美子「戦争遺跡を活用した『地域まるごと博物館』構想」
(『月刊社会教育』通号 62 号、2007 年6月)
・愛沢伸雄「戦跡をまちづくりに活かした館山市でのこころみ」
(『土木施工』通号 657 号、2011 年9月)
*関係者への聞き取り
・NPO法人安房文化遺産フォーラム代表愛沢伸雄氏・事務局長池田恵美子氏
(2011 年 11 月 16-17 日、2014 年 2 月 14-15 日)
・館山市教育委員会生涯学習課文化財係長杉江敬氏(2011 年 11 月 17 日)