「女子教育の殿堂」ぜひ!国の文化財に
「安房高等女学校木造校舎」 有志ら署名活動
館山に1930年建築 白鳥のような美観
(東京新聞 2025.3.15.)-c-142x300.jpg)
千葉県指定有形文化財の旧県立安房南高校(館山市北条)の第一校舎を補修など適切に保存して活用し、国指定文化財へ格上げしてほしいと、NPO法人安房文化遺産フォーラムと「安房高等女学校木造校舎を愛する会」が6日、知事、県教育長宛てに要望書を出した。(山本哲正)
県立安房高等女学校は安房南高の前身で、1930年に建てられた。愛する会は、旧第一校舎を地域の誇りとして後世に継承、活用を願う有志らで、フォーラムを事務局として2017年に発足。敷地の草刈りや校舎の清掃、また調査、記録などの活動を続けている。
同会によると、旧第一校舎は、関東大震災を教訓に技術の粋を集め、和洋折衷で優れた意匠を施された。左右対称に大きく羽を広げた白鳥のように美しい姿は、女子教育の殿堂にふさわしいとされた。戦後、安房南高となった。
鉄筋造りに変わる時代に、保存された木造の旧第一校舎は、1995年に県指定有形文化財となった。だが、2008年に学校統合で閉校し、日常的には使われなくなったという。
同校には、明治期以降に先駆的な女子教育が果たされてきたことなどの貴重な教育資料も多く残されている。歴史的価値は高く、木造校舎は学校博物館としての活用も期待される。一方で閉校から時がたち、校舎は塗装の剥げや損傷も進んでいる。
同会は、県から委託を受けていた見学会が24年度から中止になり、文化財建物の放置と劣化を懸念して、署名運動を展開。要望書は「市、県、国と地域住民が一丸となって文化遺産を未来に継承するため、国指定文化財への格上げを要望する」としている。
要望書に添えられた署名は紙、オンラインで計3,156人分。引き続き署名を募っている。オンライン署名は=QRコード=から。問合せは、安房文化遺産フォーラムの池田恵美子さんへ。
安房南高校旧第一校舎の保存活用と国文化財への格上げ求め
2団体が県と県教委に要望書と署名提出 館山
-262x400.jpg)
(房日新聞 2025.3.9.)
NPO法人安房文化遺産フォーラム(愛沢伸雄代表)と安房高等女学校木造校舎を愛する会(片方義明会長)は6日、館山市北条の県指定文化財「安房南高等学校旧第一校舎」の保存活用および国指定文化財への格上げを求め、県と県教委に要望書と3156筆の署名を提出した。
同校舎は、関東大震災を契機に耐震構造で建設され、古い日本の木造建築と西洋建築の要素が融合したデザインが特徴だ。1930年に建築されたこの校舎は、中央に玄関があり、左右対称に広がる外観が当時の学校建築の典型を示している。木造2階建ての構造は欄間付き格子窓が並び、開放的な雰囲気を醸し出している。95年3月に県指定の文化財となった。
校舎は2008年に学校統合により閉校。その後、校舎を管理する県教委では一般公開を行ってきた。18年からは地元の安房文化遺産フォーラムが県教委から委託を受け、安房高等女学校木造校舎を愛する会と協力して、校舎の公開を実施してきた。23年の公開には地域内外から約760人が訪れ、校舎内に残る貴重な教育資料などを見学した。
しかし、24年からは防火設備の問題で公開が中止され、現在は維持管理が行えない状況にある。
両団体は、保存と適切な管理を求め、昨年7月から署名活動を開始。用紙とオンラインで計3156筆の署名が集まった。また、要望書には、他地域の先進事例を参考に、文化財を生かしたまちづくりの一環として、国指定文化財への格上げの必要性も訴えている。
要望書と署名は同日、愛沢代表と片方会長が館山市コミュニティセンターで県文化財課の職員に手渡した。
片方会長は、「一般公開で訪れた卒業生たちの喜ぶ姿が忘れられない。ぜひとも、再び校舎の開放を実現してほしい。また、来場者の笑顔が見たい」と述べた。また、愛沢代表は「校舎は地域にとって魅力的なランドマーク的存在であり、文化財として保存・活用することは地域活性化につながる」と語った。
両団体では引き続き多くの市民らに賛同を得るべく署名活動を展開していく。オンラインでの署名は二次元コード=画像=から。
木造建築の伝統美に感銘
旧安房南高木造校舎の一般公開に760人
(房日新聞 2023.11.22付)-400x363.jpg)
県指定有形文化財の旧県立安房南高校木造校舎(館山市北条)で19日、一般公開が行われた。地域内外から760人の来場があり、木造の建築美や同校の歴史に触れ、見学を楽しんだ。
郷土の文化財の理解を深めるとともに、文化財を活用したイベントとして県教委と安房高校が毎年実施している。NPO法人安房文化遺産フォーラムが企画運営し、安房高等女学校木造校舎を愛する会が協力した。
続きを読む »»
11月19日 ゆかりの作品や制服も展示
(房日新聞 2023.10.22付)@-312x400.jpg)
館山市北条の旧県立安房南高校木造校舎の見学会が11月19日、開催される。校舎内を自由に見学できる他、同校にゆかりのある美術作品、制服の展示なども行われる。入場無料。
郷土の文化財の理解を深めるとともに、文化財を活用したイベントとして県教委と安房高校が毎年実施。NPO法人安房文化遺産フォーラムが企画運営し、安房高等女学校木造校舎を愛する会が協力している。
同木造校舎は、関東大震災の教訓をもとに、耐震構造建築として古い日本の木造建築と当時の新しい西洋建築の要素を融合させ、1930年に建築された。
左右対称に大きく羽を広げたようなデザインや、菱形を重ねたレリーフや窓の飾りなど、建設当時の様子をよくとどめており、昭和初期の県の学校建築の姿を今に伝える建物として、95年に県の有形文化財(建造物)に指定されている。
同NPOでは「貴重な地域遺産として、木造校舎を未来に手渡しましょう」などと、多くの来場を呼び掛けている。
時間は午前10時から午後3時まで。予約は不要だが、混雑状況によって入場制限をする場合がある。
駐車場は県南総文化ホールの第1駐車場が利用可能。靴を入れる袋と上履きを持参する。また、感染症対策として手指消毒、マスクの着用を推奨している。
問い合わせは、安房文化遺産フォーラム(090―6479―3498)へ。
旧県立安房南高校第1校舎公開
1930年造 木造校舎のぬくもり
(毎日新聞2022.11.11付)
_page-0001-300x214.jpg) 県指定有形文化財に指定されている旧県立安房南高校第1校舎(館山市北条)が10月29,30両日に一般公開された。2008年に県立安房高校に統合後、NPO法人「安房文化遺産フォーラム」などが保存活動を続け、年1回の見学会を開いてきた。台風15号被害と新型コロナウイルス感染拡大の影響で19年以降は中止が続いてきたが、今年は4年ぶりに公開することができた。
県指定有形文化財に指定されている旧県立安房南高校第1校舎(館山市北条)が10月29,30両日に一般公開された。2008年に県立安房高校に統合後、NPO法人「安房文化遺産フォーラム」などが保存活動を続け、年1回の見学会を開いてきた。台風15号被害と新型コロナウイルス感染拡大の影響で19年以降は中止が続いてきたが、今年は4年ぶりに公開することができた。
現存する第1校舎は1930年に建てられた。木造2階建てで1116㎡。薄いピンク色の建物が左右対称に伸びる外観は、羽を広げた白鳥に例えられる。日本の伝統的木造建築と洋風建築が融合した和洋折衷の設計で、当時としては最新の耐震技術が施されているという。
各教室には歴代の制服や落書きが残る机や椅子などが展示され、見学者たちは熱心に見入っていた。70年に安房南高を卒業したという館山市の加瀬久子さん(71)は「在学中は意識しなかったが、年齢を重ねるうちに、素晴らしい環境瀬青春期を過ごしたと気付いた。卒業生ではなくても、木造校舎のぬくもりに触れ、母校を大切にする気持ちを思い出してほしい」と話していた。
(房日新聞2022.11.5付)⇒ イベント詳細 ⇒ 木造校舎の魅力

県指定有形文化財の旧県立安房南高校木造校舎(館山市北条)の見学会が29、30日、開催された。台風被害、コロナ禍を経て4年ぶりに現地での開催となり、2日間で延べ520人が来場し、旧南高校の歴史や木造の建築美などに触れた。
同校舎は、関東大震災の経験を生かした耐震構造建築で、古い日本の木造建築と当時の新しい西洋建築の要素を融合させ、1930(昭和5)年に建てられた。建設当時の様子をよくとどめており、昭和初期の県の学校建築の姿を今に伝えているとして、95(平成7)年に県の有形文化財(建造物)に指定されている。
一般公開は、郷土の文化財の理解を深めるとともに、文化財を活用したイベントとして県教委と安房高校が主催。2018年からNPO法人安房文化遺産フォーラムが企画運営し、「安房高等女学校木造校舎を愛する会」が協力している。
コロナ禍を受けて予約制での開催となった今回は、安房地域の他、県内外からも申し込みがあり、にぎわいを見せた。さまざまな時代の制服や授業道具、写真、資料、安房地域にゆかりのある美術作品などの展示の他、動画上映なども行われた。来場者は、展示物をじっくりと見学、細部に見られる建築装飾にも目を凝らしながら校舎内を巡っていた。
西郷力さん(81)=神奈川県平塚市=は「初めて中に入った。素晴らしい木造建築を守りながら、何かに活用して多くの人が足を運べるといいですね」。妻で同校卒業生の登志子さん(79)は「卒業以来で懐かしいと思うとともに、当時は気付くこともなかったが、こんなに価値あるところで学んでいたんだと実感している。今後もぜひ保存していただきたい」と思いを話していた。
(房日新聞2022.10.6付け) ⇒-214x400.png)
県指定有形文化財の旧県立安房南高校木造校舎(館山市北条)の見学会が29、30日に開催される。台風被害、コロナ禍を経て4年ぶりに現地での開催となる。定員は午前、午後各200人(1組4人まで)で、事前申し込み、日時指定制で入場は無料。11日まで受け付けている。
木造校舎は、古い日本の木造建築と当時の新しい西洋建築の要素を融合させ、1930年に建てられた。建設当時の様子をよくとどめており、昭和初期の県の学校建築の姿を今に伝えているとして、95年に県の有形文化財(建造物)に指定されている。
一般公開は、郷土の文化財の理解を深めるとともに、文化財を活用したイベントとして県教委と安房高により毎年実施。NPO法人安房文化遺産フォーラムが企画運営し、安房高等女学校木造校舎を愛する会が協力している。
内容は、40分程度の所要時間で、校舎見学の他、写真や資料による地域の歴史紹介、館山市ゆかりの芸術家の作品展示、校舎案内の動画上映などを予定している。
申し込みは、29、30日の午前、午後のいずれかを選択し、インターネットの専用フォーム=QRコード=か、往復はがきで。往復はがきの場合は、代表者氏名、住所、電話番号、人数、希望日時を記入の上、NPOフォーラム安房南見学会係(〒294―0045館山市北条1721―1)へ送付する。
問い合わせは、NPO法人安房文化遺産フォーラム(0470―22―8271)へ。
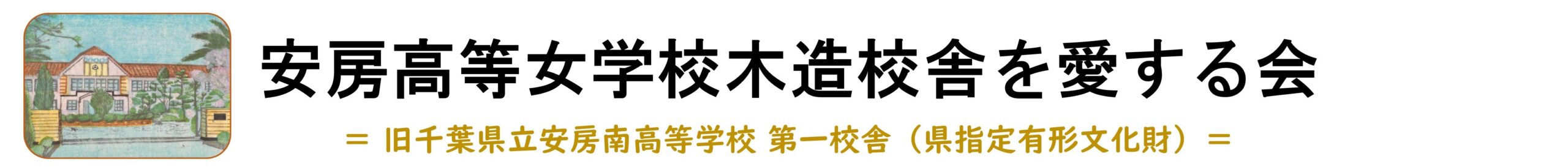
-c-142x300.jpg)
-262x400.jpg)
-400x363.jpg)
@-312x400.jpg)
_page-0001-300x214.jpg)

-214x400.png)